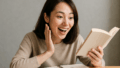共感導入パート:「疲れに効く」って本当?
「栄養ドリンクで疲れがとれる」はウソ?——そんな記事タイトルを見かけて、思わず「なるほど、そうだったのか~」と、どこかの番組ナレーションのように納得してしまいました。
実際、私自身も「疲労回復のためにいい」と言われてきた方法をいくつも試してきました。
たとえば、夜勤明けの帰りに立ち寄った温泉やスーパー銭湯。体を休めたつもりが、むしろどっと疲れてしまって、帰宅後はぐったり……なんてこともしばしば。
また、疲れを吹き飛ばそうとジムで体を動かしたのに、翌日には足が重く、やる気が出ない。よかれと思ってやったことが、どうも裏目に出ている気がして、モヤモヤした経験が何度もあります。
疲労に関する情報は巷にあふれていて、「サプリがいい」「スタミナ料理で元気を出そう」「熱めのお風呂でリフレッシュ」など、一見納得できそうなものばかり。
でも、どうしてそれで「本当に楽になる」とは限らないのでしょうか?
今回は、そんな「よかれと思ってやってきた疲労回復法」の中にある、思わぬ“落とし穴”について、看護師としての経験と実感を交えながらお話ししていきます。
あなたの疲れが本当に癒えるためのヒントになるかもしれません。
① 「効いた気がする」だけ? 栄養ドリンクの罠
「これ一本で疲労回復!」という言葉に惹かれて、私も栄養ドリンクを何シーズンか試していた時期がありました。
夜勤前や長時間勤務の朝など、疲れそうなタイミングに飲むと、たしかに目が覚めるような感覚があり、「よし、まだ頑張れる」と思えてしまう。
実際、職場でも「疲れてるときはこれ」という雰囲気があり、私自身も半ば“お守り”のように常備していた記憶があります。
でも、何度か試していくうちに気づいたのは、「効いたと思って動き続けたことで、むしろ疲れがどんどん蓄積していった」という反動の感覚でした。
一時的に楽になったように感じても、それはカフェインや微量のアルコールによる覚醒作用であって、疲労そのものが回復したわけではありません。
しかも、動けてしまうぶん、「まだ大丈夫」と誤解してしまい、休むべきタイミングを逃していたことにもあとから気づきました。
疲れていることに気づかないまま動き続ける——それが一番、怖いことなのだと、今では思います。
② 温泉・運動・サウナ…「癒やし」だと思っていたものが実は?
休日に温泉やサウナ、適度な運動で「リフレッシュしよう」と考える人は多いと思います。
私も、仕事でくたくたになった日の翌日、「温泉でスッキリしよう」と出かけたことがありました。
ところが、温泉から帰ったあとは、かえってぐったり…。移動や混雑の疲れもあり、「全然休んだ気がしない」と感じることが多かったんです。
熱めのお湯に何度も浸かること、長時間のサウナでの発汗。これらは一見、デトックス効果があるように見えますが、実は自律神経に大きな負担をかけていることもあるそうです。
運動も同様で、「体を動かせばスッキリする」と信じていましたが、疲れているときほど動くことで逆に交感神経が優位になり、心身の緊張状態が長引いてしまう場合もあります。
特に運動中は、脳内麻薬(エンドルフィンなど)が分泌され、一時的に疲れや痛みを感じにくくなるため、「元気になった」と錯覚してしまいがちです。
つまり、「快感=回復」ではないということ。
体を動かすことや温泉が悪いわけではないのですが、“今の自分にとって必要な刺激かどうか”を見極める視点が、もっと必要だと感じています。
疲れているときこそ、「あえて何もしない」という選択が、自分を守ることにつながる場合もあるのです。
③ スタミナ食やサプリへの過信
「疲れてるなら、うなぎでも食べて元気つけなきゃ」「焼肉でスタミナ回復!」というような言葉、よく聞きますよね。
実際、私も夜勤明けや連勤続きのとき、「たんぱく質をしっかり摂らなきゃ」と思って焼肉に行ったり、ビタミン剤やBCAAのサプリを飲んだことがあります。
でも、正直言うと、「なんだか胃がもたれて、逆にしんどくなった」という記憶の方が強いんです。
現代人の食生活はすでに栄養過多気味で、疲れたからといって無理にスタミナ食を摂ると、消化吸収に余計なエネルギーを使ってしまい、かえって体に負担をかけることもあります。
また、サプリメントについても、「なんとなく効きそう」という期待感で飲んでいる人は多いのではないでしょうか。
しかし、例えばビタミンCやB群の摂取は、過剰になってもすぐ排出されるだけですし、BCAAやアミノ酸系サプリにも「飲めば即元気になる」ような魔法はありません。
むしろ、本来の栄養バランスが崩れるほどサプリに頼ると、自己調整力が落ちていくという指摘もあります。
サプリメントも食事も、あくまで補助的なものであって、「元気の源」はやっぱり、休息と質のよい睡眠にあると、私は感じています。
④ 「ちゃんと寝たのに疲れが残る理由」=睡眠の質の問題
「昨夜はしっかり7時間寝たのに、なんだか体が重い……」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
私はあります。しかも、一晩ぐっすり眠ったはずなのに、起きてから体がだるくて、なかなかエンジンがかからない。
この原因の一つが、「睡眠時間の長さ」ではなく、「睡眠の質」にあるということを、最近よく耳にします。
たとえば、交感神経が高ぶったまま布団に入っても、浅い眠りになりやすく、脳や身体の本当の回復には至らないことも。
私も夜勤明けなど、頭がぼーっとしたまま寝落ちしたときは、寝たのに疲れが取れない感覚をよく経験しました。
また、寝る直前までスマホを見ていたり、部屋が明るすぎたり、カフェインが残っていたりすることで、メラトニンの分泌が妨げられ、深い眠りに入れないという指摘もあります。
「ただ横になれば休める」ではなく、「心身が整った状態で眠る準備をする」ことが、疲労回復には大きく影響するのだと、今は実感しています。
⑤ 看護師視点で見えた「本当に効いたセルフケア」
疲労回復に対して、いろいろな方法を試してきた私が、最終的にたどり着いたのは、「整えること」こそが回復の鍵だという考え方でした。
看護師として、そして一人の生活者として、何が自分に本当に効いたのかを振り返ってみると、共通していたのは「無理なく、自然にできること」でした。
たとえば、ぬるめのお風呂。
熱いお湯に何度も入るのではなく、ぬるい温度で10〜15分ほどゆったりと浸かるだけで、副交感神経が優位になり、寝つきも良くなるのを実感しました。
また、軽い散歩も効果的でした。がっつり運動するのではなく、朝の光を浴びながら10分歩くだけでも、気分が整う感じがありました。
意外だったのが、呼吸を意識すること。
深呼吸を数回するだけでも、肩の力が抜けて、自律神経が落ち着く感覚があることに気づいたのです。
そして、水分補給も見直しました。カフェイン飲料を控え、水や白湯をゆっくり飲むことで、身体の調子が整いやすくなりました。
これらはどれも、「頑張る」ことではなく、「整える」ことを意識した行動です。
仕事や家事に追われていても、意識ひとつで取り入れられる小さな習慣が、じわじわと効いてくる——。
それが、現場の中で、そして自分の暮らしの中で感じた実感でした。
⑥ まとめ:習慣を見直して“本当の回復”を手に入れよう
私たちはつい、「疲れたら何かを足さなきゃ」と考えてしまいがちです。
栄養ドリンクを飲んだり、がんばってジムへ行ったり、あれこれと頑張る方向に意識が向いてしまう。
でも本当に必要なのは、「整える」という視点なのかもしれません。
身体が求めているのは、刺激ではなく、安心できる環境とリズム。
派手な対処ではなく、静かな回復。
かつて私は、「30歳までに夜勤はやめる」と決めたはずでした。
でも今、再び深夜や当直の勤務をしている現実に、どこかで違和感を覚えています。
体の声を聞くという意味でも、「整える」ことの大切さを改めて感じる日々です。
もし今、あなたが「疲れが抜けない」「頑張ってもスッキリしない」と感じているなら——
足すより整える。
この視点を、今日から少しだけ取り入れてみませんか?
小さな習慣が、明日のあなたの元気を支えてくれるかもしれません。